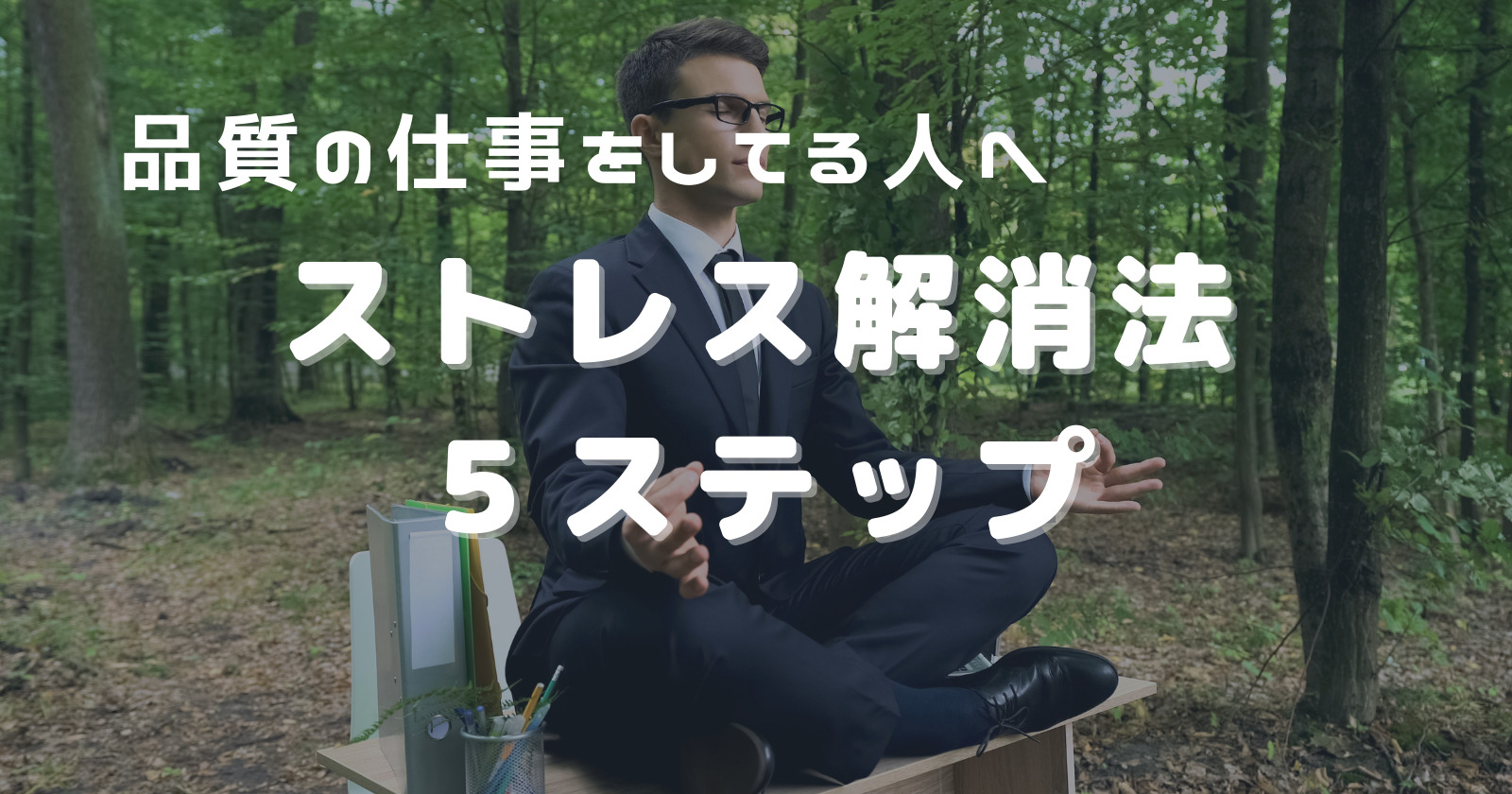製品の品質に携わる仕事をしていると、お客様からのクレーム対応は切っても切れないものです。
クレームが帰ってこないことが1番ですが、現実はなかなかにキビシイです(^^;

クレームって、どうやって対応すれば良いんだろ?
納得してもらうためには、クレームが発生した原因や問題をわかりやすく説明して対策する。「同じ問題はもう起こりません」と宣言することが大切。
その1つの手法として、8Dレポート(エイトデイ-レポート)があります。
余談ですが、始めて8Dレポートって聞いたとき、8日以内に提出するレポート!?って間違ってました(恥^^;)
実際は、8つの【D】=Desciplineの略称でDesciplineを調べると「規律、しつけ、訓練、懲罰、自制心」などが出てきます。
ちょっとピンときませんので、あまり気にせず8つのステップくらいに思っていてOKです。
この記事では、8Dレポートの具体的な書き方を解説します。
- クレーム対応で報告書を作成している人
- 8Dレポートをこれから作成しようとしている人
YouTubeの解説動画はこちら
8Dレポートの具体的な書き方


8Dレポートには、D0~D9まで決められた9つのステップがあります。1つ多いですが、ここではD0を付け加えてます。
実際レポートを書いてみると、D0があった方がわかりやすいです。
- D0:クレームの情報、お客様からの情報整理
- D1:問題解決チームの結成
- D2:問題の理解(不具合の観察)
- D3:暫定の処置
- D4:根本原因の調査・特定
- D5:是正処置
- D6:是正処置の効果検証
- D7:再発の防止
- D8:お客様の承認(チームの解散)
8Dレポートの報告フォーマットに決まりはありませんが、Excelで1枚にまとめているものや、Wordを使っているところもあります。
個人的なオススメは、PowerPointです。
1つのスライドに1つの言いたいことを書いて、スライドを増やしていくと、情報を整理しつつまとめることができます。別のクレームでも、中身を差し替えるだけで、使い回すことができて便利です。
それではD0~D8の中身を解説していきます。
D0:クレームの情報、お客様からの情報整理
お客様から頂いたクレームの情報をそのまま使用します。
8Dレポートには、おおよその期限が設定されています。クレームの受付日からカウントが始まりますので、日付も大切な要素になります。
お客様との契約や、会社の方針があると思いますので、その点は確認が必要です。事例を紹介するとこんな感じです。
| ステップ | かけられる日数 | 合計日数 |
|---|---|---|
| D0:クレームの情報 | 3日 | 受付 |
| D1:問題解決チームの結成 | ↓ | ↓ |
| D2:問題の理解(不具合の観察) | ↓ | 発生から3日目 までに報告 |
| D3:暫定の処置 | 4日 | ↓ |
| D4:根本原因の調査・特定 | ↓ | 発生から7日目 までに報告 |
| D5:是正処置 | 7日 | ↓ |
| D6:是正処置の効果検証 | ↓ | ↓ |
| D7:再発の防止 | ↓ | ↓ |
| D8:お客様の承認(チームの解散) | ↓ | 発生から14日 でクローズ |
日付は、会社休日を除いた営業日の日数です。
D0ではお客様の報告書から必要な部分を抜き出して記載します。
- クレームの受付日
- お客様での発見日
- クレーム品の写真
- お客様で何が発生したか
- クレーム品はどこで見つかったか
D1:問題解決チームの結成
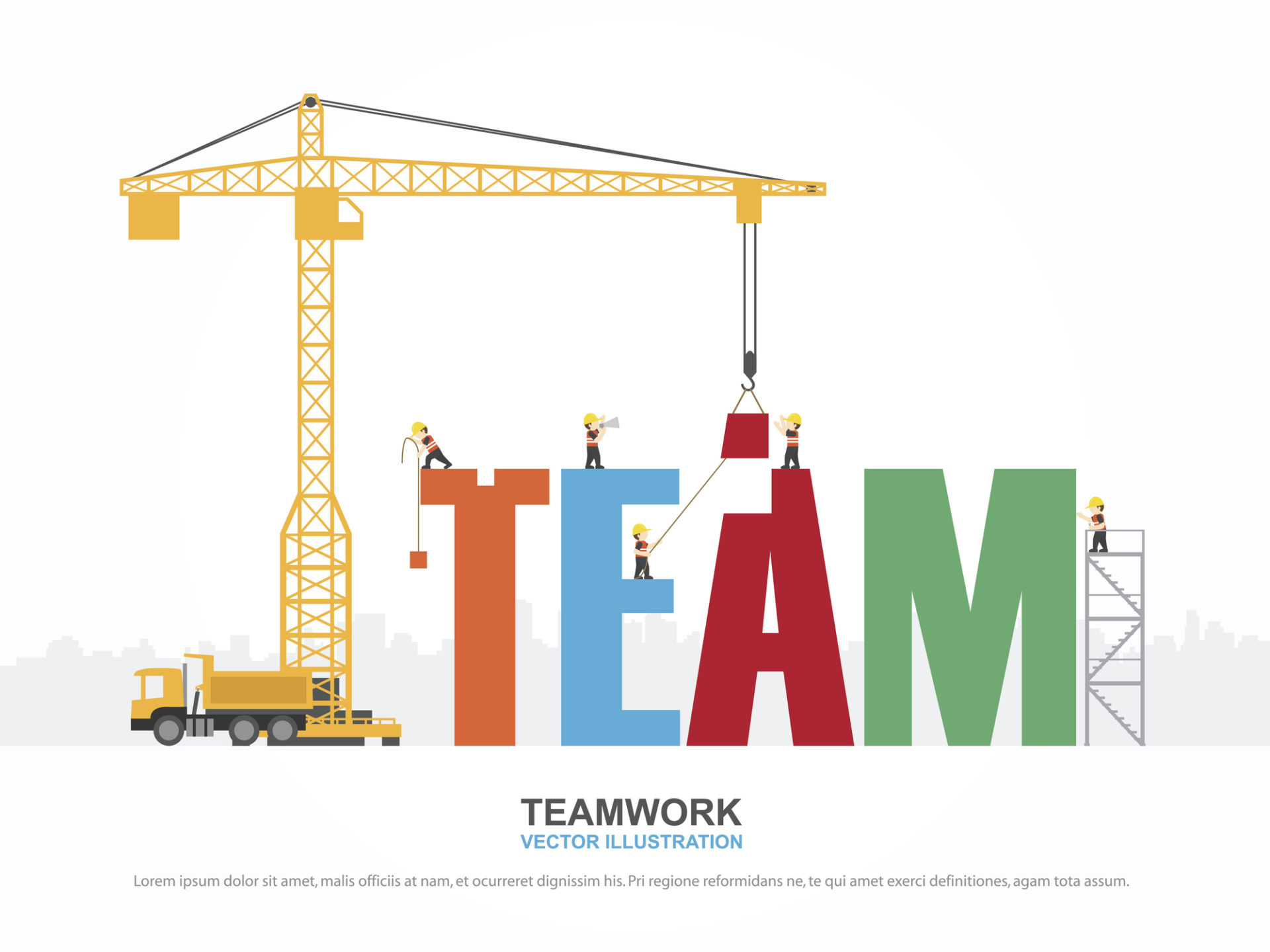
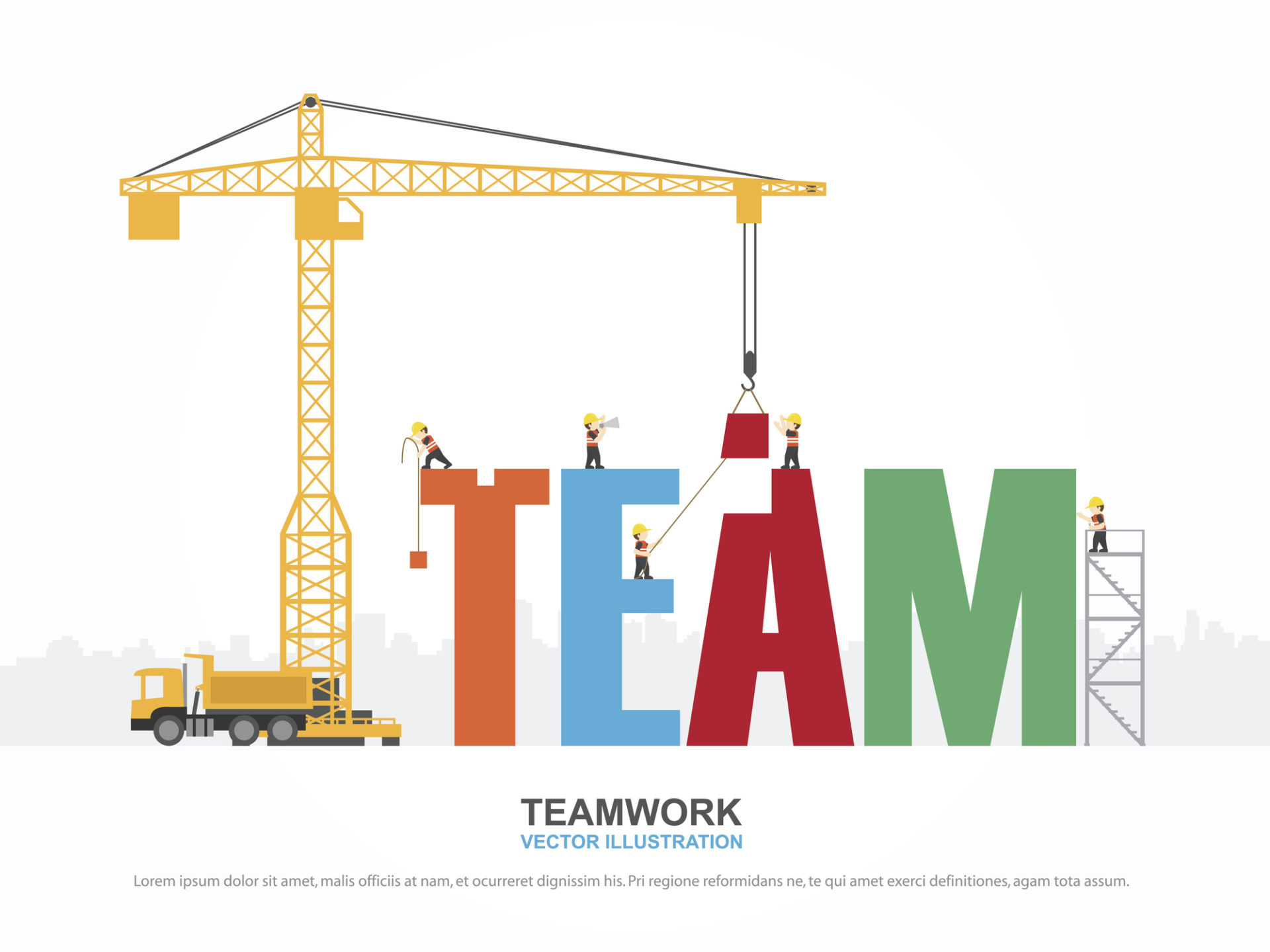
最初にクレームの問題を解決するメンバーを選出します。
メンバーは、各部門から選出する必要があります。品質、技術、製造、設備など、各グループから部門横断的に編成します。
リーダーは、クレームを受け付けた時点でメンバーを招集、クレーム情報の説明とチーム結成の意志を伝えることが大切です。
15分のミーティングをするだけで、問題解決は飛躍的に加速します。(1回目のミーティング)
D2:問題の理解(不具合の観察)
このステップで、クレーム品を調べた結果を詳細に書いていきます。
一般的にクレーム品は返却されますので、お客様が言っている不具合の事象が間違っていないかを自社で再度観察します。
観察の方法は、不具合の内容になって違ってきますが、原因を追求するために正しい観察は不可欠です。
例えば商品にキズがあった場合を考えると
- キズの長さは何cm?
- キズの深さは何cm?
- キズの幅は何cm?
- キズの場所はどのあたり?
- キズの状態を顕微鏡で見て、切り口を観察する
どんな観察をするのか?も解決チームで決めます。(2回目のミーティング)
D3:暫定の処置
このステップは、クレームを受けて、今製造している製品や商品はそのままで良いのか?を考えます。
まだお客様に届けていない製品・商品は、在庫として作っているケースがほとんどです。
D2で商品のキズの例を出しましたが、在庫品とこれから作る製品にキズがないことを確認して出荷する必要があります。
原因が分かるまでは、製品・商品が大丈夫!と保証する処置を決めます。(2回目のミーティング)
D4:根本原因の調査・特定


このステップでクレーム品の観察結果や事象から原因を特定します。原因を特定するためのステップは、次のようにやっていくと解決できます。
クレームに繋がった問題が発生する可能性があるものを全て書き出します。
いくつか手法はありますが、経験上1番良い方法は、FTA(故障の木解析)です。似たものに特性要因図=フィッシュボーン(魚の骨)がありますが、日本人には少々使いづらいです。
やっていることは同じなので、やりやすい方法でOKです。
FTAは別記事で使い方を解説してます。
洗い出した要素1つ1つに対して、原因になるかを協議します。(3回目のミーティング)
判断は、データや過去の記録など、数字で表現できるものから客観的に行います。定量的に判断できない要素は、一旦「△:判定保留」にして、データ収集もしくは取得する作業を行います。
最後まで要素として否定できない項目が、原因の可能性になります。まだこの時点では原因とは特定しません。
抽出した原因の要素から、どうやって問題が発生するかを考えます。
例えば「商品にキズがあった」というクレームを考えてみます。
このときFTAから「商品を搬送するレールの上に、商品と接触する部品があった」、そして「その部品を止めていたネジが外れていた」が原因とします。
この1連の流れを図や写真、絵を使って、分かりやすく説明するフェーズになります。
発生メカニズムで説明した事象が、本当に起こるのか?を検証するステップです。
再現させることが難しいことも良くあります。その場合は、擬似的な再現試験でも大丈夫です。
データ的には、何回試して、何回再現した!と表現することも、発生率や波及性を考える上で大切です。
クレームの不具合が、メカニズム通りに再現できれば原因は確定します。
原因は確定しますが、ここでその原因は根本原因か?を考えます。
ここで紹介した事例「ネジが外れていた」は根本原因ではありません。なぜネジが外れていたか?を深掘りした先にあるものが根本原因になります。
ここで「なぜなぜ分析」というツールが出てきます。なぜなぜ5回と良く言いますが、センスを問われる難しいツールです。簡単に書くと、こんな感じです。
| なぜ1 | なぜ、ネジが外れていた? | ネジ山が磨耗していた |
| なぜ2 | なぜ、磨耗していた? | ネジを交換していなかった |
| なぜ3 | なぜ、交換してなかった? | 交換するルールがなかった |
| なぜ4 | なぜ、ルールがない? | ルールは必要ないと考えていた |
| なぜ5 | なぜ、必要ない? | リスクは小さいと考えていた |
- ネジを定期的に交換する
- 定期交換のルールを作る
- ネジが緩むと商品に不具合が発生するリスクに加える
実際は、こんなに簡単には行きません。なぜなぜ分析はかなり難しいです^^;
なぜなぜ分析のやり方は、こちらの記事で解説してます。
D5:是正処置
なぜなぜ分析から導き出された根本原因に対する対策を書きます。
対策の内容と開始日が書かれていれば大丈夫です。
対策が書かれた内容が、文書化されたものを貼っておくと信頼度がグッと上がります。
D6:是正処置の効果検証
対策が的外れでないことを検証します。
対策実施日から数日間モニタして、不具合が発生していないことを数字で表します。
効果検証に時間がかかる場合もありますが、レポート上は一定期間の数量を母数にした結果で判断することが多いです。
D7:再発の防止
今回の問題を再び発生させないために、どうするかを書きます。
具体的には、FMEA(故障モードと影響分析)にリスクとして追加する方法が効果的です。
FMEAに追加するときは、他の装置や工程などにも横展開することも重要になってきます。
FMEAの使い方は、こちらの記事で解説してます。
D8:お客様の承認(チームの解散)
クレームに関する8Dレポートをお客様に提出して、了承してもらえれば今回の問題解決はクローズです。
承認頂いた日を明確にして、チームを解散します。
8DレポートでD8を直訳すると「チームの称賛」ってなりますが、あまり馴染めないので気してません(^^;
まとめ:9つのステップで問題を解決する
8Dレポートは、9つのステップで問題を解決して、報告書にまとめたものです。
- 9つのステップ(D0〜D8)
-
- D0:クレームの情報、お客様からの情報を整理する
- D1:問題を解決するチームを結成する
- D2:問題を理解するために、不具合品を観察する
- D3:今作ってる製品を保証するために、暫定の処置を実施する
- D4:根本原因の調査・特定を行う
- D5:是正処置(根本原因の対策を行う)
- D6:是正処置の効果を検証する
- D7:再発しない予防策を実施する
- D8:お客様の承認(チームを解散する)
最初は難しく感じるかも知れませんが、順番に1つずつやっていけば、論理的に問題にアプローチできます。
クレームの報告書として、8Dレポートは一般的に使われるようになってきました。お客様から8Dレポート様式で提出して!と言われることも多いと思います。
これから8Dレポートを作成する方の参考になれば嬉しいです。
最後までお付き合い、ありがとうございました。<(_ _)>