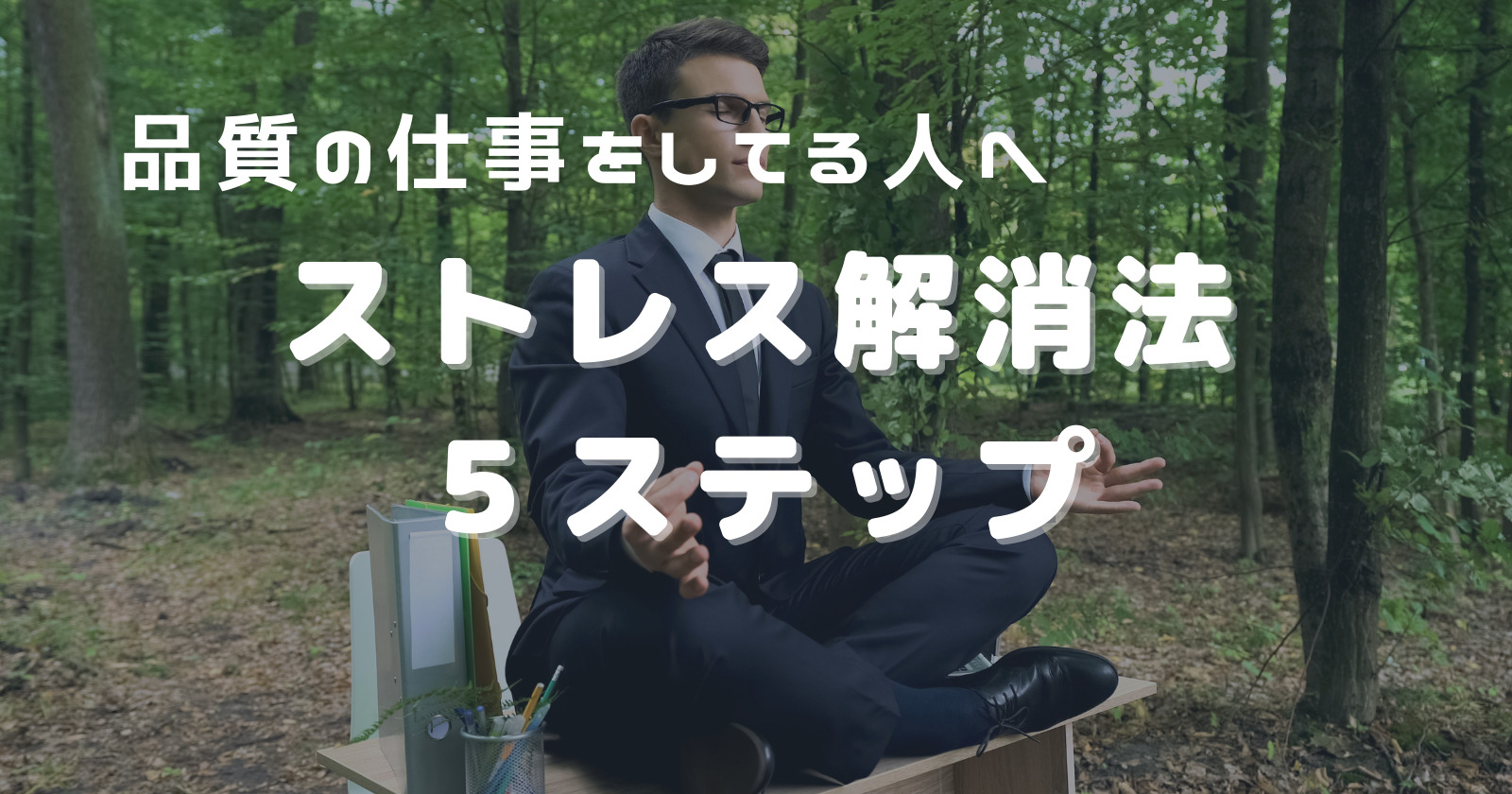製造業の工場で25年ほど品質管理の仕事をしてますが、ヒューマンエラーは悩みのタネの1つ。

手が滑って、製品落としちゃいました・・・



違う材料を使っちゃった・・・



めんどうだから、この作業やらなくてもいいか!
いろんなタイプのヒューマンエラーがあるけど、その対策はなかなか難しい。
いま現場で起こる事故やトラブルの原因は、だいたいヒューマンエラーが絡んでます。(ポカミスって呼ばれることもあります)



ヒューマンエラーって、どんなミスをいうの?
ヒューマンエラーの定義はいくつかあるかも知れませんが、僕は「人がたずさわった作業のミス」だと考えています。
そのミスが大きいと事故やトラブルにつながります。小さいとヒヤリハットと呼ばれる事故の予兆になります。
車の交通事故を考えると、事故の99%以上は「ヒューマンエラー=人の操作ミス」によって発生してます。
- ブレーキと間違えてアクセルを踏んでぶつかった!
- 赤信号を青信号と間違って交差点に入った!
すべてドライバーが起こした事故。交通事故は、年々減少傾向にありますが、ゼロにはほど遠い。そのことがヒューマンエラーを無くす難しさを証明してます。



ヒューマンエラーをゼロにするのって無理なの?
ゼロは無理でも、ゼロに近づけることは可能です。この記事では、ヒューマンエラーを効率よくゼロに近づける方法を紹介します。
- ヒューマンエラーが多くて困っている人
- 現場で品質管理の仕事をしてる人
ヒューマンエラー対策が難しい理由


なぜ、ヒューマンエラーの対策は難しいのでしょうか?
多くの場合、ヒューマンエラーの原因にたどり着かずに、小手先の対策をすることになります。
小手先の対策とは、人が頑張って、気合でミスを出さないようにするような類(たぐい)です。気合は、3ヶ月は持ちますが、1年もすると同じ問題を繰返します。
ヒューマンエラーの原因をしっかりと見て、適切な対処をしていくことが大切です。
ヒューマンエラーの種類は、大きく4つ!
- ルールを知らない
- ルールを守らない
- ルールが守れない
- 無意識
それぞれの内容と対策を解説していきます。
車の交通事故を例にすると分かりやすいので、たびたび車のたとえ話が出てきますが、ご了承下さい m(_ _)m
ルールを知らない


「赤信号は止まれ」を知らなければ、当然交通事故が起こります。シンプルですが、ヒューマンエラーで1番多い原因です。でも本人には、まったく悪気がありません。
「赤信号は止まれ」は、小さい頃からみんなに教えてもらってます。保育園の先生、幼稚園の先生、小学校でも警察の人がきて交通ルールを教えてくれます。
なんども繰り返し教えてもらうことで、「赤信号は止まらないとダメ」を知らない人はいません。
工場でも、これと同じことをすればいい!
ルールを知らないのは、教育が不足しているから。教育が不足している理由は、
- 教材がない
- 教材を作っても、教育する人(先生)がいない
- 先生を作っても、教育する時間がない
この解決策は、「先生を作って教育する時間を確保する」です。
でも解決策は分かっていても、なかなか実践できません。



なんで、実践できないの?
経営者から見ると、教育している時間、教育されている時間は利益を生みません。
- 専用の先生を作っても、先生には生産性がありません。
- 生徒も授業を受けている時間は生産(作業)してない。
結果、利益につながりません。
当然、経営者は新人を採用すると即戦力で使いたがります。十分に教育する時間なんて、そもそもないことが多い。
経営者が考え方を変えない限り、いくら現場が頑張っても無理な問題です。



じゃあ、どうしようもないよぉ
どうしようもない問題ですが、良いところもあります。それは時間が解決してくれるところ。
ルールを知らない人も、失敗を重ねることで徐々に覚えていきます。6ヶ月もすれば、自然とヒューマンエラーは無くなってくれる救いがあります。
- ルールが変わらない
- 新しいルールができない
- 新人が入ってこない
ただ、実際はそんなことはありません。ルールも変われば、新人さんも入ってきます。何か変化が起こるたびにヒューマンエラーが起こってしまいます。
このことは経営者も知っていて半分目をつぶっているはず。そこを理解しておくと、ストレスが溜まらなくなります^^;
ヒューマンエラーの撲滅に熱心な経営者がいれば
- 専任の教育担当者を作る
- 十分な教育時間を確保する
この2つで問題は解決します。
「ルールを守らない」ヒューマンエラー


ルールは知ってるけど、故意にルール通りにしないでミスをするケースです。
- 制限速度60kmの道路を100kmで走行する
- 黄色信号から赤信号に変わる交差点にスピードを上げて通過する
だいたい「楽がしたい」という気持ちが行為にでます。
人は、楽をしたい生き物。効率を上げるという気持ちならOKですが、単に面倒だからしないとNGです。
ヒューマンエラーを集計すると分かってきますが、発生させる人がだんだん固定されてきます。注意しても、ルールを守らない人は一定数います。
日本は、組織で責任を取る風習があるので、意外と罰則がない会社は多いです。僕の会社でも、故意にヒューマンエラーを起こしても、明確な罰則ルールはありません。
故意のヒューマンエラーを無くすには、事故が発生したときの処分を明確にして、意識を変える活動をします。
もう1つのアプローチとして、モチベーションを上げる方法があります。
直接対策ではありませんが、モチベーションの低い現場はヒューマンエラーが多いです。具体的にモチベーションを上げる方法は、3つ。
- 福利厚生を充実させる
- 給与を上げる
- 承認欲求を満足させる
具体的な方法は、こちらの記事で解説してます。
「ルールを守れない」ヒューマンエラー
ルールを守る意志はあるのに、ルールを守れずに起こったミスです。
具体的には3つのケースがあります。
- ルール自体がない
- ルール自体が間違っている
- 仕事量が多くて1人で対応できない



ルールって、具体的になにを指すの?
ルールとは、みんなが共通に認識・理解できるもの、企業で言えば文書化した標準書(手順書)です。
①ルールがない、②ルール自体が間違っているケースは、最初に修正が必要です。
- 標準書(手順書)を作る
- 標準書(手順書)を正しい作業に修正する
- 標準書(手順書)に時間を入れる
言葉にするのは簡単ですが、実現はなかなか難しいです。ここでも「ルールを知らない」と同じで経営者の考え方が大切になります。
標準書作りには、多くの時間が必要です。別の仕事をしている片手間に作るため手順が抜けていたり、間違ったりします。
専任の教育担当者を作れば、教育してる以外の時間で、標準書作りをしてもらえます。やはり大切なことは、経営者がいかに目に見えない品質にコストをかけることができるかだと思います。
「無意識」のヒューマンエラー


熟練した作業者が、正しい作業をしたと思ってるのにミスすることがあります。
「なぜ、ミスをしたか?」本人にも分かりません。「魔が差した」という表現をすることもあります。
この対策は、機械にアシストしてもらうのが有効です。「ポカヨケ」と呼ぼれているものです。
具体的なポカヨケの例
- バーコードによる現品確認
- 自動的にデータがダウンロードされる
- カメラ認識を使って検査を行う
などなど
人の作業を機械・ロボット・システムに変えていくイメージです。ミスが起こっても、人の作業ではないので、ヒューマンエラーになりませんし、原因・対策も明確にできます。
人を減らすことも出来るため、人件費削減、利益upの為、経営者のこの部分に1番力を入れてます。
まとめ:ヒューマンエラー対策は地道な活動
ヒューマンエラーには4つの種類があります。その原因と対策は次のようになります。
| 種類 | 原因 | 対策 | 根本対策 |
|---|---|---|---|
| ルールを知らない | 教育の不足 | 専任の教育担当を作る | 経営者のやる気 |
| ルールを守らない | 楽をしたい意識 | 罰則作り | ー |
| ルールを守れない | ルール作りが不十分 | 専任の教育担当を作る | 経営者のやる気 |
| 無意識 | わからない | 機械化 | ー |
ヒューマンエラーは、経営者を巻き込んで活動しないとなくなりません。
よくトップから「ヒューマンエラーをなくせ!」って言われることがありますが、逆に反撃(アドバイス)ができます。
変にストレスをかかえることもありません。
ヒューマンエラーで悩んでいる人も、自分の性にすることはありませんので、地道に活動していきましょう^^
最後までお付き合い、ありがとうございました。<(_ _)>